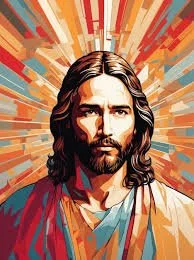伝説の戦いの父: 私の人生物語
こうして私は、精神と心理の戦いで世界一になった......。
私は1986年12月26日、ペンシルベニア州フィラデルフィアで生まれた。私の両親はキャンディ・ショップを経営していたが、父はIVYリーグのウェストミンスター神学校で学んでいた。父は長老派の牧師になるために勉強していました。私と家族全員がニューヨークのクイーンズに引っ越したのは、私 )が3歳、姉が4とき当時、私の家族はとても貧しく、父が教会を建て始めたばかりだったからだ。両親は厳格で、私は牧師の息子として、またクリスチャンの信者として、常に模範となるようプレッシャーをかけられていました。髪型、宝石、服装、世俗的な音楽を聴くなど、他の問題児がやっているようなことは許されなかった。教会に迷惑をかけたこと、特に礼拝に出席しなかったこと、協調性がなかったことで、父から何度も叱られた。ベイサイドのM.S.158という中学校に通っていた私は、最後の学年になる前ごろ、グレートネック・ノースという学校に転校した。この世代には、韓国系アメリカ人や中国系アメリカ人のゴング・メンバーや、トライアドと呼ばれるチャイニーズ・マフィアが大勢いた。銃の撃ち合いもたくさんあったし、コカインやエクスタシーを中心としたドラッグにはまっている人もたくさんいた。グレートネック・ノースはオタク学生ばかりで、当時はまだ未熟だった私のタイプではなかったからだ。グレートネック・サウスは、ベイサイドやフラッシングと同じように法律問題を起こす生徒が多かったので、両親は私を行かせませんでした。そこで2、3ヶ月勉強した後、私はもう嫌になり、母にベイサイド高校に行かせてくれるよう懇願した。しかし、私が本当に望んでいたのは、問題を起こす友人たちと一緒にいることだった。韓国人と韓国系アメリカ人という環境で育った私にとって、彼らは唯一の友人だった。母は私の願いを叶えるため、ベイサイド高校に転校させた。転校してまだ3ヵ月も経っていないのに、私は学校をサボり、悪い仲間とつるんでいた。このことは両親にとって深刻な問題で、私がタバコを吸い、他の生徒と何度もストリートファイトをするようになった。若い頃からマリファナを大量に吸ったり、ドラッグを売ったりしていた友人も多く、彼らは学校の警備員や特に警察との問題に直面していた。その時私は2年生で、両親は私がこのまま高校を卒業するのは無理だと考えていた。そこで両親は、私をキリスト教系の全寮制高校に送り出すことにした。父から聞いたのは、言うことを聞かなくてもいい場所だということだけで、私はそれを自由だと誤解していた。だから、その年頃の私は世の中のことをほとんど知らなかった。後になって、この場所全体についてとても奇妙な雰囲気を感じたので、家出を決心したんだ。その日は韓国のお祭りがあって、フラッシングには韓国人や韓国系アメリカ人が大勢いて、韓国から多くの歌手がニューヨークに来てパフォーマンスをしていた。韓国オリンピックがあって、文字通りベイサイドとフラッシングの町の人たち全員がフラッシング・メドウ・パークに集まったんだ。私は3日間家を空けていたので、タバコを吸い放題、酒を飲み放題で自由に過ごすことができた。お金を持っていなかったので、友達とレストランで食事をして、お金を払わずに逃げました。フラッシング・メドウ・パークには、フライング・ドラゴンやゴースト・シャドウズと呼ばれる敵対する中国人ギャングもたくさんいて、僕の知っている友人の何人かはエクスタシーを過剰摂取して入院した。また、ベイサイドでは、私の義理の兄がddrストアを経営しており、多くのトラブルメーカーが集まってドラッグでハイになりながらレイブしまくっていた。最後の夜、私は焼酎を5~6本飲んだ後、友人の家で寝ていたのですが、朝になって玄関のドアをノックしている私をなぜか母が見つけました。母が言うには、寄宿学校に行くか、父がエスコーターを送って引っ張ってくるかのどちらかだという。だから、私は素直に行くしかないと決心した。学校のキャンパスはミズーリ州ストックトンにあり、空港のあるカンザス・シティに着いた後、私と母は近くのモーテルで寝た。その夜、私は興奮すると同時に緊張もした。というのも、このような状況を経験するのは初めてだったからだ。学校の入り口に「アガペ寄宿学校」と書いてあった。田舎にあり、農場のような環境とたくさんの動物がいたので、私はここが楽なところだと大きく見くびっていた。正面玄関のドアから中に入り、母が院長の奥さんと話していると、2人の巨大な男が近づいてきて、私は別の部屋に通された。母が泣きながら玄関から出て行ったので、私と母はきちんと別れを言う機会さえなかった。スタッフは私のニューポート・タバコを没収し、オレンジ色のTシャツに青いジーンズを着せた。それは、ブートキャンプに参加する生徒のカラーコードのひとつだった。キリスト教の寄宿学校が、これほど恐ろしい収容所のような環境になるとは思ってもみなかった。髪型は坊主にするか、横分けにするかのどちらかだった。私の髪はすでに剃られていたので、変える必要はなかった。カフェテリアに入ると、私のようなオレンジ色のシャツか黄色のシャツを着た数百人の学生が2人、バーゲンディを着ていた。黄色のシャツは、ブートキャンプを卒業し、高校卒業資格を得るために学校に通う生徒のためのものだった。バーゲンディシャツの生徒も学校に通っていたが、バディステータスであれば、オレンジシャツやイエローシャツよりも権限があった。バディ・ステータスのルールは、新入生や下位ランクの生徒がプログラムのルールを学び、それに従うことができるようにするためのモードだった。下位の選手たちは、文字通り3フィート(約1.5メートル)離れてはならず、バーゲンディシャツの前で24時間365日常に後ろを振り返っていなければならない。初日は、15年間生きてきた中で最も大変な日だった。他の6、7人のブートキャンプメンバーと一緒にキャンパス全体のグラウンドの雪かきをしなければならず、その上、大量の激しい運動をしなければならなかった。翌朝、ベッドから動けないほどきつかった。腕立て伏せ、レッグリフト、スクワット、クランチ、クァンザハットでの往復スプリントを300回ほど繰り返した。私は生まれつき、そして遺伝的に強く、その年齢で腕相撲で負けたことはなかったが、それでも大苦戦した。この時、私は自問自答した。「と自問自答し、自分を憐れんだり、父を責めたりして気持ちを楽にしようとしても、余計に自分を追い詰めるだけだった。2001年の12月、私は16歳の誕生日をここで過ごし、生き地獄を味わった。故郷の友人たちが好きなことをしている姿しか見えず、たとえ200人の生徒がいたとしても、私はとても孤独を感じていた。肉体労働はまさに収容所のような環境で、このプログラムのモットーは「自分を壊し、自分を立て直す」だった。重労働ばかりだったが、食事はとてもおいしく、寮の部屋とベッドは暖かく快適だった。母が3ヵ月間、私を家に連れて帰るために侵入してくるのではないかと、窓や正面玄関のドアをこっそり見たものだが、そんなことはなかった。面会は3カ月に1度で、3カ月目からは家族宛ての電話や手紙のやり取りはすべて許可された。スタッフは、私たちが手紙を読んだり送ったりする前に、すべての手紙を読んだ。3ヵ月後にブートキャンプを卒業したとき、私はついに母から初めてVisitを受け取った。私は自分の目を疑い、駆け寄って今までで一番大きなハグをした。韓国料理がなかったので、母はカップヌードルと韓国焼肉を持ってきてくれた。母と一緒にいるとき、私は母に故郷に連れて帰ってくれるよう懇願したが、計画と期待通りにはいかなかった。私たちは一緒にビリヤードをしたり、フルーイズボールで遊んだりした。初めての訪問だったので、キャンパスの外に出ることは許されなかった。それでも私たちは一緒に充実した時間を過ごした。ホットチョコレートやコーヒーを飲むことが許されたのは、面会などの特権があるときだけだった。たった3日間の面会だったが、母と過ごした時間の中で最も適格だったと言わざるを得ない。日目、最後の日、私は自分の置かれた状況について深く考えた。私たちは全員、水曜日はチャペル、日曜日は教会に出席しなければならなかった。ブートキャンプを卒業した今、私は学校に行くことを許され、オレンジ色のシャツの次のランクである黄色のシャツを着ることができた。このプログラムの学校は、故郷の公立学校とは違い、先生からレクチャーを受けるのではなく、歩数で勉強するものでした。私が長く学校に通う機会がなかったのは、大規模なハリケーンに襲われ、全校生徒が重労働を強いられたからだ。私たちは、ハリケーンが吹き飛ばした木や石、重い建築部品の破片をすべて運び、キャンパスがあまりにも巨大だったため、2、3マイルも運ばなければならなかった。疲れて地面に落とせば、何度も体操をさせられ、その直後に持ち上げてはまた落とし、また体操をさせられた。自分の母親を鉛筆で刺してこのプログラムに送られた13歳の生徒がいたが、この時はストレスのあまり、従順であることを拒否して地面に落下してしまい、マニオクのように罵り始めたので、スタッフが彼を拘束して別室に連れて行った。スタッフの中には、元海兵隊員、元特殊部隊員、元用心棒、元重量級ボクサー、元重量級リフティング選手、さらにはミズーリ州の保安官までいた。主任牧師でさえ、かつてはボクシングのヘビー級チャンピオンだった。生徒たちが寄宿学校から逃げ出そうとしたことは何度もあったが、学校の歴史上、家に帰り着いた生徒は1人だけで、護衛官を通して送り返されただけだった。多くの生徒がここに送られたのは、少年院では財産を扱えないため、セカンドチャンスを与えるために、法律でここに来るよう命じられたからだ。私の世代が2番目に厳しかったのは、規則があまりにも厳しく過酷だったため、プログラム全体がカリフォルニア州のストックトンから追い出され、代わりにミズーリ州に移ったからだ。肉体労働と規律訓練があまりにも残酷だったため、生徒たちが強くなりすぎて手に負えなくなったのだ。私の時代には、自由時間に運動して体を作るために重いウェイトを持ち上げることが許されなかったのはこのためだ。重たいものを持ち上げたりするのは、短時間の懲罰的なものであったり、主要な筋肉が強くなりすぎないように、あれこれと運動するためのものであったりした。高校生という年齢では、私たちの身体は年を重ねるごとに強くなるのが早くなっており、スタッフやプログラム・ファンデーションの責任者もそれを知っていた。ほとんどの生徒が薬物やギャング関連の問題でここに送られ、残りの生徒は親への反抗心からここに送られた。私にはカリフォルニア州ロサンゼルス出身の従兄弟がいたが、その後、ニューヨーク州ロングアイランド出身の従兄弟もできた。私たちは家族ぐるみの付き合いで、互いに顔見知りだったため、隔離措置がとられた。南カリフォルニア出身の韓国系アメリカ人は50人以上いましたが、クイーンズ・ニューヨーク出身は3人だけでした。私はとても家に帰りたかったが、その日は6カ月目になるまで来なかった。私は母に、このプログラムは見かけとは違って、正確にはとても怖いところだと言い続けた。生徒の家族が訪ねてきたとき、彼らが目にするのは、私たち生徒がカラフルな服を着て、幸せそうに笑っている善良な生徒に見えるような髪型をしている姿だけだ。そして、拷問のような重労働や懲罰的な運動をしている姿は見られない。家に写真を送るときでさえ、私たちは笑顔で送らざるを得なかった。なぜなら、怒っているような悲しい表情をすると親が心配し、契約が終わる前に家に連れ戻される可能性があるからだ。回目の訪問の日、私は母に保釈され、公立の学校で一生懸命勉強すると約束した。すべてが終わったと思った矢先、私はまた学校を休み、大量のタバコを吸うことになった。まだ3日しか経っていないのに、それを知った父は、私をアガペの寄宿学校に送り返すことを決めた。もう一度家出することも考えたが、2度目のアガペ寄宿舎で受けた仕打ちの厳しさを知っていた。だから、たとえそのプログラムが一番行きたくない場所だったとしても、仕方なく協力することにした。プログラムに戻ると、またブートキャンプに戻された。これが私の人生の終わりかと思い、寮の部屋で寝ていると何度も悪夢にうなされた。全校生徒がスタッフに詰め寄り、きっぱりと脱走する姿を想像したものだ。多勢に無勢とはいえ、スタッフの方がどれだけ強いか。その後、私と同郷の生徒がプログラムに参加するようになり、一緒に逃げ出すことになりかねないということで、私たちも留守番をすることになった。一緒にプログラムに参加してしばらくして、私たちは時々こっそりと話をした。彼は「モミングパイ」、通称「mmp」と呼ばれるギャングの6代目だった。最初は中国系アメリカ人のギャングだったが、後に韓国系アメリカ人と合併した。同郷ということもあり、よく一緒に逃げる計画を立てたものだ。動物がたくさんいる森の中を通り抜けなければならなかったし、警察が捜索中だったし、現金もクレジットカードも持っていなかったから、とても大変だった。それ以前に、すべての建物と寮のドアには厳重な警備が敷かれており、学校の全スタッフが文字通り常に私たちを見張っていた。また、キャンパス全体が有刺鉄線で囲まれており、職員は全員キャンパス内に住んでいた。ある日、僕と彼がお互いに逃げようとメモを渡し合っていた時、2人とも捕まって靴を取り上げられ、ブートキャンプに送り返された。靴を取り上げられるルールは、逃げようとしたり、逃げようとするような印象をスタッフに与えたりした生徒に適用される。私たちの普通のスニーカーやドレスシューズは、足の2倍はあるボロボロのスニーカーに取り替えられ、靴の舌は切り落とされた。それは、歩行を支える上部がない巨大なスリッパの上を歩くようなものだった。また、口止めのリストバンドをつけさせられ、2週間ずっと壁と向き合わなければならなかった。一般的に、私たちが一語一語話すこと、そして手話や身振り手振りも含めて話すことすべてを、文字通り私たちのすぐそばで聞いて監視しているスタッフがいない限り、生徒同士で話すことは許されなかった。壁に向かっている間、私はプログラムだけでなく、家に帰っても、自分の何がいけなかったのか、たくさん考えた。ソファーで泣いている母の姿を想像した。生徒たちは皆、毎朝朝食を食べる前に聖書を読み、毎週水曜日にはチャペルに出席し、日曜日には教会に行かなければならなかった。ある日、聖書とにらめっこしているうちに、何となく詩篇と箴言の章にたどり着いた。そして、あることが私の興味と関心を引き、知恵について深く考えるようになった。韓国語で私の名前の最初の一文字は知恵を表し、両親は私が大人になったとき、私を大いに使うことを神に約束しながら名付けた。知恵とは何なのか、私にはよくわからなかったが、この崇高な力を得たいと思ったのは確かだ。私は3歳の頃から神を信じていましたが、アガペ寄宿学校に来るまで洗礼を受けたことはありませんでした。ある日、救いについての説教を聞き、イエス・キリストを個人的な救い主として正式に受け入れることにしました。何度も何度もタバコを吸いたくなりましたが、吸うしかありませんでした。ここに来て6ヵ月目に、母は私をもっと緩やかで重労働のない別のプログラムに移すことにした。 そこはニューヨーク州北部にあるフリーダムビレッジというところだった。このプログラムで唯一気に入らなかったのは、問題を抱えたティーンエイジャーを対象としたキリスト教のプログラムだったため、喫煙も禁止されていたことだ。そこで出会ったアンドリュー・パークという男は、私と同郷の韓国系アメリカ人で、以前はmmpというアジアのゴングのメンバーだった。彼は少年院からここに送られたんだ。彼は少年院に入所して数週間で退所してしまった。このプログラムはとてもいい加減なものだったので、生徒たちに滞在を義務づけることはなかった。だから、私はグレイハウンドのバスに飛び乗って帰ってきた。それを聞いた父は動揺し、怒り心頭で、もし私がアガペの寮に戻ったらどうなるか、よく分かっていたので、どうしたら私をアガペの寮に戻せるだろうかと悩んでいた。私が数日間家にいると、両親はある計画を思いついた。それは、私にはアガペ寄宿舎に親しい従兄弟がいるので、母が私を置いて行くとは知らずに、休日に母と一緒にその従兄弟を訪ねに行くというものだった。私は何が起こるかまったく知らなかったので、喜んで母と一緒に行くことにした。正面玄関に入ると、5人の大きなスタッフが私に声をかけ、母は涙を流していた。その時、私は今自分が何に巻き込まれたのかを理解し、また自分が直面することになるなんて信じられないと思った。私はブートキャンプに戻され、面会もできないまま10カ月もそこにいた。問題を起こしてブートキャンプに落とされ続け、逃げ出そうとしていたからだ。そのため、学校で勉強する機会もなかった。精神的にも肉体的にも苦労の多い数カ月で、16年間の人生でこれほど神に祈ったことはなかった。4ヵ月余りいる間に、私は気を取り直して厨房で無給の仕事に就いた。そのため、スタッフは常に私を監視していた。このプログラムは、刑務所よりもさらに管理が難しく、北朝鮮の収容所に近かったからだ。もうすぐ18歳になるし、どうせ期限内に卒業証書を受け取る方法はなかったからだ。プログラムから抜け出す方法は、親が保釈してくれるか、卒業するか、法的に18歳になるかの3つしかなかった。18歳になれば、スタッフは何もすることなく、合法的に玄関から出て行くことができる。この瞬間、私は世界で最も幸せな人間だったと言わざるを得ない。母に空港まで送ってもらう間、私は20回以上もスタッフに追いかけられていないか、文字通り車の後方を振り返った。ホットココアやアイスコーヒーを飲むといった些細なことでさえ、当たり前だと思っていたことが、とてもありがたいことになりました。私にとって、アガペの寄宿学校は現実であり、現実の世界に戻ってくると、まったく別の世界にいるように感じました。私が経験したトラウマのような出来事は、自分で体験しない限り、誰にも本当に理解することはできないし、知ることもできない。それは永遠に続く旅の新たな始まりだった。プログラムの厳しい規則に縛られることに慣れていた私は、2、3日の間、母にお風呂を使ってもいいかとしきりに聞いていた。そのため、母はそこがどのような場所なのか知らなかったのだと思い知らされた。しかし、母はいつも私の部屋に入ってきて、私がいないところで私の衣類に触れ、それでも母はそれを知らず、息子が孤独で恐ろしい場所にいるため、まともに食事もできなかったのだ。私は18歳になるまであと数ヶ月だった。アガペ寄宿舎学校を卒業できなかったので、ランニング・スタート・プログラムのある専門学校に通い、大学のコースを学んだ。ここに通う前は、他の知り合いが大学に通っていたり、まともな仕事に就いていたりする中、私は一人で他の州を旅して、学歴も高卒資格も持たずに生き残る道を探そうとした。私はまず、職業訓練を受けると同時にG.E.D.を取得できるジョブ・コープ・プログラムに通った。そこはオレゴン州にあり、滞在中はほとんど毎日、一日中雨が降っていた。世界中から同じ目的で集まった人たちは、30歳という年齢制限を設けていた。まるで30歳という年齢が、この時代では尊敬される年齢であるかのようだった。ここではタバコを吸うことも許されていたが、私はどうしても勉強したくなかった。私は約2年間、高校卒業資格もG.E.D.も持たずに生きていく方法を見つけるために、州から州へと旅をしていた。ジョブ・キャンプ・プログラムを辞めたとき、グレイハウンド・バスでワシントン州シアトルに行き、ホームレス・シェルターの上に小さなワンルーム・アパートを借りた。そこで私はヴァージニアに行き、そこで同郷の別の友人に誘われ、私と彼ともう一人の彼の友人とでジョニー・ウォーカーの酒をたくさん飲み、タバコを吸いまくった。彼らはマリファナ・ジョイントをたくさん吸ったが、私は吸わなかった。母が心配していた。それで私はグレイハウンド・バスでニューヨークに戻った。マンハッタン、ペン・ステーションにあるテクニカル・キャリア・インスティテュート・スクールに戻った。当時19歳だった私は、27歳の中国人女性に出会った。彼女は僕と同じクラスで、二人ともクイーンズのフラッシングに住んでいたので、一緒に7番の電車に乗った。私は彼女と正式に付き合うことになったが、母の目には彼女はとても怪しく映った。彼女には中国に夫がおり、私がアメリカ市民であったため、グリーンカードを取得するために偽の結婚証明書を偽造しようとして私を利用していたことも知らなかった。また、彼女がトライアドという中国マフィアの関係者であることも知らなかった。TCIカレッジでその中国人の女の子に出会う前、私はmmpという韓国系アメリカ人と中国系アメリカ人のストリートギャングに所属する大問題児だった。モーミング・パイとは、中国語でノー・ノーム・ギャング、韓国語でムー・ミョン・パという意味だ。mmpギャングはフラッシングの2大ギャングを敵対視しており、フライング・ドラゴンとゴースト・シャドウズと呼ばれていた。この3つのギャングは売春宿、賭博場、ルームサロン、ナイトクラブ、バーなどを牛耳っていたから、縄張りの奪い合いから何度も喧嘩になった。僕はmmpに入る前からゴースト・シャドウズと友達だったんだけど、ある日、誤解が生まれたんだ。公園のベンチでゴースト・シャドウのメンバーたちと一緒に座っていたら、冗談で「自分たちのギャングになって、mmpから出て行かないか」と誘われたんだ。私は断ったが、彼らは理解してくれた。しかし、mmpのメンバーの一人が嘘をでっち上げ、私がmmpを裏切ってゴースト・シャドウズに加わったと、ダイローと呼ばれるmmpのギャングのリーダーに話した。彼は公園のベンチで私を見つけ、首根っこをつかんだ。彼は "なぜそんなことをしたんだ?と聞かれたので、「やっていない」と答えたが、彼は納得しなかった。それでギャングのリーダーは私の後頭部を叩いて殺そうとしたんだけど、運良く白人のおばあちゃんが "Say You're Sorry!"とギャングのリーダーに向かって叫んだんだ。 その瞬間、すべてが止まった。知らず知らずのうちに彼女を遣わし、奇跡的に私を救ってくれた神に感謝した。問題児の友人はたくさんいたが、結局のところ、私にふさわしい友人ではなかった。こうして神様は、私をこのような生活や生き方から救い出してくださったのです。 また、ナイトクラブで知り合ったもう一人の友人がいたが、彼はチャイニーズ・マフィア、トライアドに所属する大の麻薬中毒者だった。私はエクスタシーとコカインが彼や他の人々に何をしたかを見てきた......神が私をその世界から連れ出してくれたことにも感謝している。ある休日、私はその少女の家を突然訪ねた。彼女の夫との会話を盗み聞きしたところ、彼女が実は既婚者で、詐欺師であり、中国の犯罪組織の一員であることがわかった。私はこの時、母が本当に正しかったことを悟った。私は、母が中国のマフィアに私を結婚させるよう送り込み、結婚させられなければ殺されるのではないかと心配し、怖くなったので、アメリカ海兵隊に入隊して逃げることにした。父は何度も、そこは私の行くところではないし、私にはふさわしくないと言ったが、私はとても頑固で従順ではなかったので、ただ聞き入れなかった。でも、私は頑固で言うことを聞かなかった。私はG.E.D.を持っていなかったし、重度のADHDだったから、軍隊に入ることさえ許されないはずだったんだけど、採用担当者はボーナスがもらえるようにそれを振りかざしたんだ。ADHDの人は、軍隊、特に海兵隊の恐ろしいほどストレスの多い環境のせいで、高い確率で精神障害に行き着く。サウスカロライナ州パリス島の米海兵隊新兵訓練所で黄色い足跡を踏んだとき、私は大きな間違いを犯したと感じた。後で分かったことだが、私は最も困難な部署、3102小隊キロ中隊第3バタリオン、キリングマシーンにいた。その時、採用担当者が私を大の女好きだとあれほど嫌っていたのは、当時の私には外見だけで、知識も知恵も人間関係のスキルもなかったのだと納得した。私は小隊の中で最も体力があり、最強というわけではなかったが、アガペで生き地獄を味わったので、生き残る術は心得ていた。当時19歳だった私が海兵隊に入隊した理由は二つだけだった。ひとつは、チャイニーズ・マフィアに殺されたくなかったからで、もうひとつは、自分の人生で何かをやり遂げたかったからだ。ブートキャンプで一番大変だったのは、スタミナの部分だった。運動に対する耐性をきちんと訓練することなく、タバコを吸い過ぎたからだ。ブートキャンプを卒業するためには、3マイルをジョギングしなければならなかったが、私は最後から2番目でかろうじて合格した。苦しくなるたびに家族の顔を思い浮かべ、がんばった。参加するのはそれほど難しくないが、低いところを知らなければ抜け出すのが非常に難しい場所であり、当時の私はそのことをほとんど知らなかった。訓練で一番リラックスできたのは、ライフル銃を撃つときだった。教官が手を引いてくれて、自分が狙う標的だけに集中できたからだ。他には、教会にいるときや、クォーターデッキで手紙を受け取っているときでした。教会という環境はとても不思議なもので、普段は教官たちが私たち新兵に地獄の雨を降らせるのに、日曜日の教会では突然、すべてが陽気で素敵なものに変わるのです。父のこと、教会のこと、そしてもちろん家族のことを、私は何度も何度も考えた。海兵隊の訓練場は、実は事前に十分に準備できるものではないことに気づいた。障害物コース、肉体訓練、ガス室、長時間のハイキングなど、私を打ちのめすようなものがたくさんありましたが、海兵隊の他の人たちと同じように、支配的であるように私の心を作り上げました。アガペと海兵隊は、私が精神的・心理的な戦いで世界一になるための究極の訓練だった。私にとって最も困難な港は、激しい有酸素運動の持久力を必要とするものでした。また、海兵隊と比べて自分がいかにもろいかを思い知らされ、肉体的にも非常に弱く感じました。しかし、私はブートコンプを卒業し、卒業式に家族が訪ねてきたときは、他では味わえないような平和で歓迎された気持ちになった。それから数日間家にいて、本隊に行く準備のために海兵隊のセンターであるMTCスクールに行きました。学校を卒業した後、私は日本の沖縄に配属された。美しい島で、小隊と一緒に走っているときに怪我をするまでは、すべてが順調だった。本来の小隊は私がイラクに到着する前日に出発してしまい、私は代わりにマラソンランナーと一緒に行動することになった。私は軍を除隊し、すべての書類を指揮系統に提出した後、軍から解放された。日本からフェリーに乗って韓国へ直行し、新しい人生をスタートさせた。韓国に行くのは2度目で、1度目は中学生の時だった。韓国には知り合いもいなかったし、1,500ドルしか持っていなかった。どうしても仕事が必要で、当時は英語を教えるか翻訳をするかしかありませんでした。そこで、地元の塾で即採用され、その後、小中学生を対象にした家庭教師もやりました。もっと給料をもらいたかったので、韓国で最も裕福な街、江南(カンナム)で輸出入会社の翻訳の仕事に就いた。そこで出会った上司は、韓国のアイビーリーグを卒業した人だった。彼は、私がお金と泊まる場所に緊急に困っていたとき、私を受け入れてくれた。当面は彼のオフィスで寝泊まりさせてもらい、その後、ボスの家に行って彼の家族に紹介された。偽の卒業証明書を偽造したときでさえ、彼は私が高校を卒業していないことを知っていたと私は今でも信じているが、それでも彼は善意から私を受け入れてくれた。私はいつも彼に真実を明かし、深く謝りたいと思っていたが、その機会はなかった。韓国での生活は人生で最も幸せな瞬間だったが、両親の病気が重く、帰国しなければならなかった。気を取り直して、もう一度TCIカレッジに通い、G.E.D.資格を取得しました。また、ナイアック・カレッジという聖書大学に2年ほど通いながら、牧師になるための勉強をし、フィラデルフィアにあるウェストミンスターというIVYリーグの大学院に行きました。しかし、私は神に仕える別の方法を見つけた。また、20代前半にはスパでシャンプー・アシスタントの仕事にも就いた。ライター業とシャンプー・アシスタントの仕事は、私があきらめなかった唯一の仕事だった。20代前半になるまで、心理戦が何なのかさえ知らなかった。私はキリスト教の本だけを書こうと思っていたのですが、自分が本当はどんな真の力を持っているのかを知ってから、霊的戦いと心理的戦いの両方について書くことにしました。このとき私は、自分がどちらの戦いにおいても世界一であることを知っていた。21歳のときから現在37歳になるまで、私は一度も負けたことがない。学校でも教会でも職場でも、社会に出ればどこでも、私はみんなを笑いものにしていた。カフェやスターバックスのコーヒーショップで、1日8~9時間という長時間、ずっと文章を書き続けながらトレーニングして資格を取り、両親でさえも奇妙に思うほど懸命に真面目に働いた。でも、それが私が最高の選手になるために必要なことだったのです。小さい頃から教会の人たちに「神様は私を大きく使ってくださる」と言われ、アイビーリーグに行った年上の姉には「アイビーリーグに行ったのはもっと年上よ」といつも言われていた。私はいつも、みんな善意で言ってくれているのだと思っていたし、ただ褒めてくれて親切にしてくれているだけだと思っていた。昔、アイビーリーグに行った私の父も、母に私のことを心理戦の天才だと言ったし、教会のメンバーには、私が生まれつきの天性としてキリスト教をマスターしていると言った。心理戦では、すべてを手に入れるか、すべてを失うかしかないので、尊敬されるのはとても難しい。私を尊敬しているという男性は3人しかいなかったが、複数の女性が私を台座に乗せるのはもっと簡単だった。ハーバード大学、コロンビア大学、プリンストン大学の精神科医や心理学者でさえ、私は勉強さえしていればアイビーリーグで世界史上ナンバーワンの学生になれただろうと言った。だから、世界一はG.E.D.卒に過ぎないという事実に、多くの人が度肝を抜かれたのだ。アガペースクールと海兵隊は、私のマインドパワーを鍛え、持って生まれたものの使い方を学ぶための神からの訓練の場だった。以前は、私は人間ではないと言う人もいた。なぜなら、私は誰の砲撃にも屈しないし、感情的になっても驚かないからだ。私は何百万人もの人たちを相手にしてきたが、私がいつも優位に立ち、女性を手中に収めているにもかかわらず、世の中のために全力を尽くしているのは事実だ。すべては私が作った文章を繰り返す戦略から始まり、それをマスターした後、私は両戦場のあらゆる知識、知恵、技術に深く飛び込んだ。それらはすべて、キリスト教、心理学、哲学、人間関係、生き方という5つの限りない核となるトピックに枝分かれしている。私はこの世を去るその日まで、神から授かった贈り物を世界中の人々に広めることに人生を捧げることを誓います。私のゴールは、この無限の波と果てしない世界の波を発展させることで、人々が私よりもさらに前進するところまで、すべての人を両戦場の天才にすることである。最初の世界は心理戦であり、次に強化された心、あるいは高度な心、そして最後が精神戦であろう。それは世界を永遠にひっくり返して変えるだろう。